中国茶は発酵度合いによって6種類に分けられます。なかでも、独特な軽度発酵を行い作られるお茶は、黄茶(きちゃ)とよばれます。本記事では、「黄茶(きちゃ)」を解説します。
黄茶とはどんなお茶?

黄茶の読み方は「きちゃ」で、中国茶の6大茶類の1つに数えられています。中国茶は茶葉の発酵度合いの違いによって6つの種類に分けられており、6大茶類とよばれます。黄茶を含む6大茶類は下記のとおりです。
・紅茶(こうちゃ)
・青茶(あおちゃ)
・黄茶(きちゃ)
・白茶(しろちゃ)
・緑茶(りょくちゃ)
1番上の黒茶がもっとも発酵度が高く、下にいくにつれて発酵度合いは低くなります。1番下の緑茶は、まったく発酵させない不発酵茶です。
上記の順序からもわかるとおり、黄茶の発酵度合いは弱めです。
黄茶という名前の由来は、独特な製造工程にあります。黄茶は「悶黄(もんこう)」とよばれる独自の工程をはさんで作られるのが特徴で、それにより水色が黄色っぽくなります。
黄茶独自の製造工程:悶黄(もんこう)
前述のとおり、黄茶独自の製造工程に悶黄(もんこう)があります。順序としては、茶葉を加熱して発酵を止めたあとに、茶葉を揉んで水分を飛ばし、乾燥させて悶黄を行ないます。最後に再度乾燥させます。
悶黄とは、茶葉を高温多湿の空間に一定期間置いておき、弱く発酵させること。
具体的には、加熱して発酵を止めた茶葉を、熱が残っているうちに少しずつ牛皮紙などの紙の間に挟みます。そして、紙ごと木箱など密閉性の高い容器の中に入れます。そのまま数日間ほど置いておくことで、茶葉が程良く発酵するのです。
この工程によって、黄茶独自の水色や風味が生まれます。
黄茶の特徴

黄茶の特徴をいくつか解説します。
発酵度が低く、緑茶に似た味わい
黄茶は発酵度合いが低いため、緑茶によく似た香りや味わいがあります。緑茶は不発酵茶ともよばれ、茶葉をまったく発酵させずに作られます。

中国茶は香りや風味の個性が強いものも多いですが、緑茶に似ている黄茶は比較的どなたでも飲みやすいお茶といえるでしょう。
やわらかい甘みとフレッシュな香り
黄茶は渋みや苦みはあまりなく、やわらかい甘みを感じられます。香りも緑茶に似たすがすがしさがあり、ほんのりフルーティーさを感じることも。
希少性が高い
黄茶は、中国茶の6大茶類のなかでも特に希少性が高いといわれています。前述の悶黄の工程に手間や時間がかかるので、どうしても大量生産しづらいのが理由の1つです。
黄茶のなかでも、君山銀針(くんざんぎんしん)という種類は非常に生産量が少ないお茶です。特に高品質の君山銀針は、中国の国外にはほとんど流通しないともいわれています。
黄金色の水色
黄茶は、その名のとおり美しい黄色の水色になります。ただし黄茶の種類によって、淡い黄色から濃い黄金色まで、色味にもグラデーションがあります。
黄茶の種類(銘柄)

黄茶のなかにも、産地などの違いによりいくつか種類(銘柄)があります。代表的な黄茶の種類をいくつかご紹介します。
君山銀針(くんざんぎんしん)
黄茶のなかでももっとも高級とされるのが、君山銀針(くんざんぎんしん)です。
水色は淡い黄色ですが、その色からは想像がつかないほどガツンとした旨みと濃厚な味わいが特徴。飲んだあとも味の余韻が長く口内に残ります。とうもろこしやたけのこに例えられる風味は、ほんのり甘みもあり絶品です。
そもそも希少な黄茶のなかでも特に生産量が少ないお茶で、中国国外にはほとんど出まわりません。
霍山黄芽(かくざんこうが)
霍山黄芽(かくざんこうが)は、やわらかく細い茶葉の新芽から作られます。その形状は「霍の舌」と形容されることも。
水色は透き通った淡い黄緑色です。さわやかな香りと、パッションフルーツや栗などに例えられるやわらかな甘みが特徴の黄茶です。
蒙頂黄芽(もうちょうこうが)
蒙頂黄芽(もうちょうこうが)は、茶葉がフラットでまっすぐな形状をしているのが特徴です。花を思わせる香りとまろやかな甘みがあり、飲んだあとも口の中に甘みが残ります。
黄茶の味や香りについて

黄茶の気になる味や香りについて、黄茶を飲んだ方の感想をXからいくつか紹介します。
すごいきれいな水色のお茶飲んでる。
姫茶伝さんの霍山黄芽。
味もさっぱりしていて、美味しい。
茶葉も美しい。 pic.twitter.com/5vTRCfaTWo— うた@うたかたの日々 (@utakatanohibi07) February 16, 2024
今日はとても暑いですね。こんな日は、「君山銀針(黄茶)」をいただきます。甘くオリエンタルなドライフルーツの香りに包まれ、口当たりは柔らかく丸みがあり、花蜜のような優しい甘さが広がります。4月の中国茶を楽しむ会では、明前の君山銀針の新茶もご用意。特別な一杯になりますように🍵 pic.twitter.com/JIRSWlFtsh
— 藤田の中国茶 (@wT59870evcTINIc) March 22, 2025
湖南省の黄茶、君山銀針。
芽の柔らかい甘みと、ほのかに柑橘系の果香。目を離したら一番の絶景を見逃した pic.twitter.com/Scmz2cbt2h— イロンダイロ (@ironda_cha) April 25, 2022
今年の君山銀針(黄針)は、ぷくっとした新芽を使って丁寧に悶黄された黄茶。深みのある蜜香、透明感と滑らかさ、とろりと甘く花蜜のような爽やかな余韻#中国茶 #君山銀針 #黄茶 pic.twitter.com/zCQjIiqiEJ
— 藤田の中国茶 (@wT59870evcTINIc) April 15, 2025
茶心居の蒙頂黄芽 めちゃ美味しい🥺✨甘くて香ばしい香りが最高、蓋裏は何故だかカカオのような香りもする pic.twitter.com/DHY59WHKlQ
— ちありー君 (@chialliekun) December 22, 2022
青蛾茶房の蒙頂黄芽 香り高く香ばしく美味しいい
直飲みは色々捗る pic.twitter.com/R4Jf7yAuyS— ちありー君 (@chialliekun) January 16, 2024
同じ黄茶でも、種類によって少し風味の違いがあるようです。君山銀針はフルーツを思わせる甘み、蒙頂黄芽はやわらかい香ばしさを感じる方も。
黄茶の美味しい淹れ方

ガラスポットに黄茶の茶葉を入れ、80度ほどのお湯を注いで蓋をし、2~3分ほど浸出させます。黄茶を淹れる際は熱湯ではなく、80度ほどに少し冷ましたお湯がおすすめです。そうすることで、黄茶特有のフルーティーな香りや、やわらかい風味が抽出されやすくなります。
もちろん急須を使ってもOKですが、黄茶を淹れる様子が美しいので、ぜひガラスポットなど透明な器で淹れてみてください。お湯を注いですぐは茶葉が上部に浮いており、時間が経つにつれて底に沈んでいきます。ゆらゆらと茶葉が沈んでいく様子は、見ているだけでリラックスできるでしょう。

山年園で販売している中国茶について
黄茶は希少価値が高いため、なかなか頻繁に飲めるお茶ではないかもしれませんが、やわらかく発酵した独特の味わいは絶品です。緑茶や他の中国茶とはまた異なる、黄茶ならではの優しい甘みを、機会があればぜひお試しください。
山年園では、さまざまな中国茶も販売しています。華やかでフルーティーな香りの中国茶を、ぜひご賞味ください。
ジャスミン茶
| 商品名 | ジャスミン茶 |
| 商品区分 | 食品・飲料 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | 緑茶、ジャスミン花 |
| 保存方法 | 高温多湿を避け湿気に注意 |
| 使用上の注意 | お早めにお召し上がりください |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 老舗のお茶屋がこだわり抜いた特級 ジャスミン茶を是非ご賞味ください(^-^)/ |
四季春
| 商品名 | 凍頂烏龍茶四季春 |
| 商品区分 | 食品・飲料 |
| 内容量 | 2g×15パック |
| 原材料名 | 茶(四季春) |
| 原産地 | 台湾産 |
| 使用方法 | 150~200cc前後の沸騰したお湯で1分強蒸らしてからお飲みください。 2煎、3煎と香り・味わいの変化をお楽しみいただけます。 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 蘭のような香りの黄金色の烏龍茶のティーパックです。 安心安全にお召し上がりいただけますので、是非ご賞味ください(^-^) |
プーアル茶
| 商品名 | プーアル茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【一袋あたり】454g |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 老舗のお茶屋の本格的なプーアル茶を是非一度ご賞味ください(^-^) |
最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)
- ダーティーラテ(ダーティーコーヒー)とは?【韓国で人気のドリンク】 - 2026年1月31日
- 抹茶の旬(新茶)の時期はいつ?季節ごとの美味しい楽しみ方も紹介 - 2026年1月30日
- 炉開き(ろびらき)とは?いつ行われる?冬の始まりをつげるお祝いの茶事 - 2026年1月29日












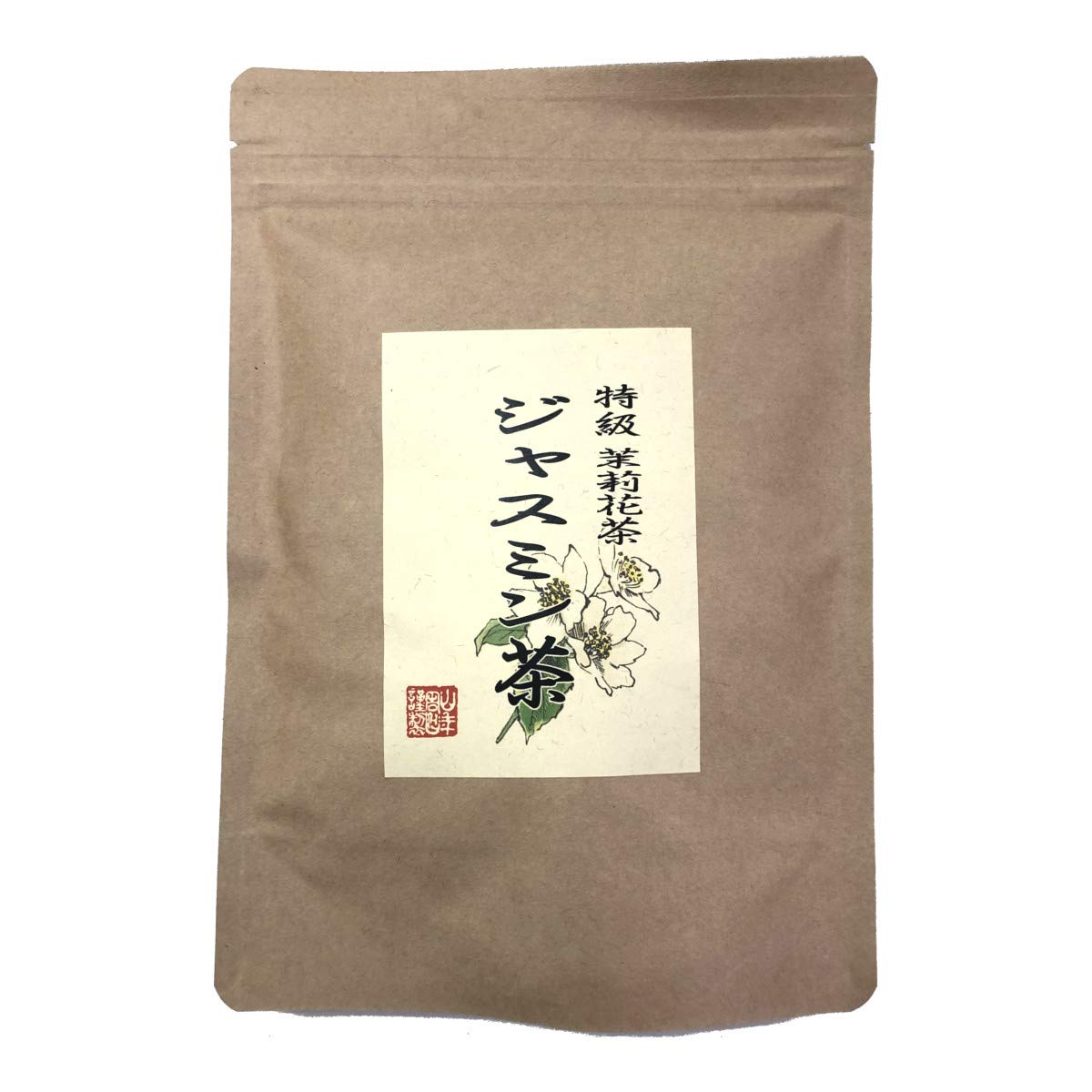

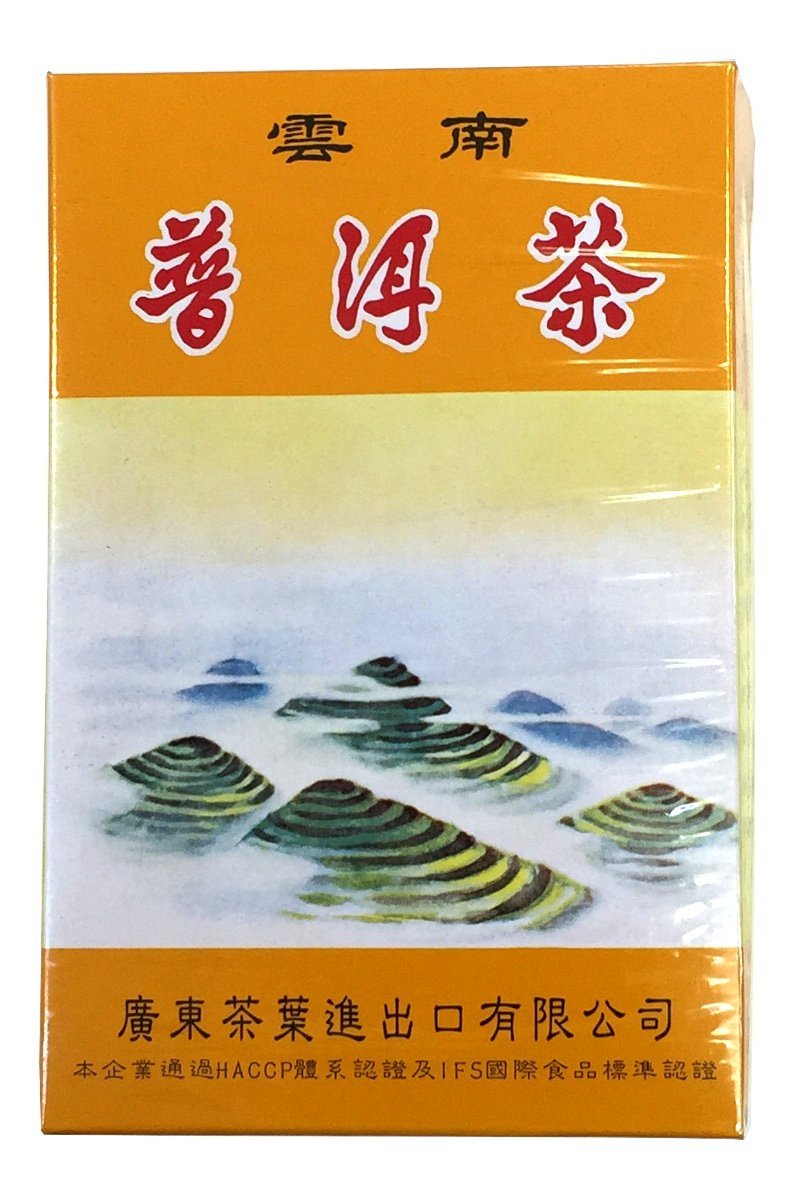


 山年園でお買い物
山年園でお買い物

