いまや海外でも人気の日本茶ですが、輸出が本格化したのは明治維新の頃。当時輸出の際に、日本茶の魅力を伝えるために一役買ったのが「蘭字(らんじ)」です。聞き慣れない言葉ですが、蘭字とは一体何なのでしょうか?
今回は、お茶の「蘭字(らんじ)」をご紹介します。
お茶の蘭字(らんじ)とは?

「蘭字」とは、輸出時にお茶を入れる茶箱に貼るラベルのこと。読み方は「らんじ」です。
「蘭」はオランダを意味するので、直訳すると「オランダの文字」という意味になります。そこから転じて、「西洋の文字」といった意味だと思われます。また、基本的に蘭字が意味するのはラベル全体ですが、ラベルに書かれた文字だけを蘭字とよぶ解釈もあるようです。
お茶輸出と蘭字の関係について
日本茶の海外への輸出は、江戸時代後期~明治時代頃にかけて本格的に盛んになりました。輸出の際に、茶箱に貼られていたA3サイズほどのラベルが蘭字で、昭和の始め頃までは使われていたようです。
ラベルといっても、ただお茶の情報が印字されていたのではありません。カラフルな多色刷りの木版画で、富士山、桜、歌舞伎役者や着物の女性など、日本を象徴するモチーフの絵がメインで配置されていました。
その絵を囲むようにお茶の種類やお茶の会社名などが英語で配置されており、非常にデザイン性の高いものでした。この絵は、当時まだあまり海外では知られていなかった日本文化を伝える、広告に似た意味もあったとみられています。
浮世絵のような日本モチーフの絵柄と、欧米風のタイポグラフィの絶妙なバランスや色使いは、日本のグラフィックデザインの先駆けとも言われるほど。ハイクオリティなデザインから、現代でも多くのファンや収集家がいます。
日本茶の輸出の歴史

もともとは中国から日本に渡ってきたお茶文化。そのお茶が国内で発展を遂げ、今では当たり前に海外に輸出されていますが、ここに至るまではさまざまな出来事がありました。日本茶の輸出の歴史を簡単に解説します。
江戸時代:初めての日本茶の輸出
江戸時代に入ったばかりの1610年(慶長15年)、世界初の株式会社ともいわれるオランダ東インド会社が、長崎県の平戸からインドネシアを経由して、ヨーロッパに日本茶を輸出しました。これが日本における初めてのお茶の輸出といわれています。
嘉永~安政時代:本格的な輸出の開始
1853年(嘉永06年)には、神奈川県の浦賀沖に、マシュー・ペリー提督が率いる黒船が来航しました。ペリーは日本に開国を要求します。
この年、長崎の女性商人であった大浦慶(おおうらけい)は、長崎の出島に在留していたオランダ人のテキストルに協力を要請し、イギリス・アメリカ・アラビアの3ヵ国に日本茶のサンプルを送りました。送られた日本茶は、今も佐賀県で作られている嬉野茶(うれしの茶)です。

3年後の1856年(安政3年)、見本を受け取ったイギリスから、貿易商人のウィリアム・オルトが来日しました。ウィリアムからの要求により、大浦慶は何と約6トンもの嬉野茶をアメリカに輸出したのです。これが、本格的な日本茶の輸出貿易のさきがけとなりました。
さらに2年後の1858年(安政5年)には、日本とアメリカの間で、日米修好通商条約が締結されました。翌年の1859年には、長崎・横浜・函館の国内3つの港が開港されました。この開港をきっかけに、日本茶の輸出が本格的に始まったといわれています。
明治時代:輸出量の急増
明治時代になると、日本茶の需要は急増しました。輸出先は大部分がアメリカで、日本茶は生糸(きいと)に次ぐ主力の輸出商品になりました。
大正時代:輸出の大幅な衰退
1914年(大正3年)から始まった第一次世界大戦の頃には、輸出が衰退したイギリスの紅茶の代わりに日本茶の需要がさらに高まり、アメリカへの輸出量もピークに。しかしそのあとの第二次世界大戦や、アメリカの紅茶消費量の増加、日本茶の品質維持の難しさなどの理由により、日本茶の生産量や輸出量は長い間大幅に減少しました。
現代における蘭字の再評価

前述のように、蘭字はただお茶の情報を記載したラベルではなく、日本茶や日本文化の魅力を伝える広告のような役割を果たしていました。
日本のモチーフの絵に、お茶の会社や種類、等級、分類など大事な情報が美しいフォントで書かれており、全体の色合いやレイアウトなど極めて洗練されたものでした。必要な情報をわかりやすく、かつ美しく配置して見せる方法は、現代の広告デザインにも大きな影響を与えたといえるでしょう。
山年園で人気の日本茶について
海外でまだ知名度がなかった日本茶を、美しいデザインで世界に広めた蘭字。今は海外でも当たり前に飲まれるようになった日本茶の発展には、蘭字の存在も影響したのです。
山年園では、日本茶や抹茶、和紅茶、中国茶などさまざまなお茶を販売しています。なかでも日本茶で特に人気が高いのが、『巣鴨参拝茶』や『とげぬき地蔵茶』です。しっかりした香りと、バランスの良い甘み・渋みがあり、どなたでも美味しくお飲みいただけます。
掛川深蒸し 巣鴨参拝茶
| 商品名 | 巣鴨 参拝茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【一袋あたりの内容量】 100g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本[Made in Japan] 静岡県掛川市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 実店舗では圧倒的に1番人気のお茶です!! 豊島区民が選んだ「豊島の名品50選」に選ばれております。 この味でこの価格のお茶は参拝茶だけとお客様によく言われます。 是非お試しください(^-^) |
とげぬき地蔵茶
| 商品名 | とげぬき地蔵茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 100gまたは200g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本[Made in Japan] 静岡県掛川市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 当店限定の巣鴨とげぬき地蔵茶です。 参拝茶と比べて、茎を抜いてあり、渋い味が特徴的です(^-^) |
最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)
- 「日本茶の日」とは?10月1日と10月31日にお茶の魅力を再発見 - 2026年1月17日
- 奈良紅茶の魅力|月ヶ瀬などの大和高原で生まれる、高品質な和紅茶 - 2026年1月13日
- 百本立て(100本立て)とは?抹茶(薄茶)をふわっと点てる茶筅 - 2026年1月6日












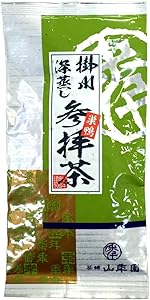
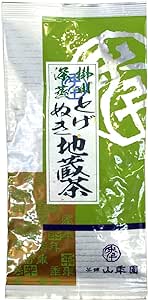


 山年園でお買い物
山年園でお買い物

