お茶は伝統の飲み物、様々な作法や独特な楽しみ方があります。
「闘茶」というお茶の遊びをご存知ですか?
闘茶とは、上流階級の間で流行ったお茶を使った賭け事です。
今では、伝統文化を知る催し物の1つになっています。
今回は、お茶の味や香りの違いを見極めて茶種や産地を当てる「闘茶」についてご紹介します。
闘茶(利き茶・茶歌舞伎・茶寄合)とは?

闘茶とは、複数のお茶を飲んでそれぞれの銘柄や産地などを見極めて当てる遊びのことを指します。
利き茶、または茶歌舞伎・茶香服(ちゃかぶき)、茶寄合(ちゃよりごう)と呼ばれることもあります。
闘茶(利き茶・茶歌舞伎・茶寄合)の歴史
闘茶の文化はいつ渡来した?

闘茶の始まりは、中国の宋から。
お茶の味や香り、泡の立ち方などを見て茶の種類を判断します。
日本では、宋から鎌倉時代後期にお茶が伝わるのと一緒に渡来したとされています。
その後、主に武士や貴族の人々の間で流行しました。
闘茶のルールの変遷
鎌倉時代には、栄西禅師が宋から持ち帰った茶の種を明恵上人が京都の栂尾高山寺に植えました。
現在では、この場所は日本最古の茶園とされ、「日本最古之茶園」の碑も立てられています。

鎌倉時代では、そこで栽培していた栂尾(とがのを)茶を本茶、それ以外を非茶として、本茶を当てるという遊び方が主流になりました。
しかし、闘茶が広まるにつれて次第に賭け事が行われるようになり、中には財を失くす人も現れるように。
この状況を重く見た足利尊氏が「建武式目」で闘茶を禁止しました。
闘茶(利き茶・茶歌舞伎・茶寄合)のルール

流派や時期によってルールはそれぞれ異なりますが、ここでは基本的な闘茶のルールをご紹介します。
闘茶は、「花・鳥・風・月・客」の名前がついたお茶を飲み、それぞれの銘柄や産地などを当てる遊びです。
まず茶葉が運ばれてきます。見るのはもちろん、香りを嗅ぐ、口に含むこともできます。
次にお茶が運ばれてきます。1つお茶を飲む毎に、自分が思う銘柄の札を投札箱に入れます。
一度入れた札は変更することができません。
5種類全部飲み終えたところで、投札箱を開けて答え合わせをします。
この一連の工程を5回繰り返し、合計点で順位を競います。
全問正解を「皆点」といい、全問不正解だった場合は「ちょっと(漢字だと、一寸/鳥渡と書く)」と言います。
闘茶(利き茶・茶歌舞伎・茶寄合)を体験できる場所は?

闘茶は、日本の寺社仏閣や茶店などで催し物として行われています。
ここでは、闘茶を体験できる場所をいくつかご紹介します。
円妙山大慶寺
- 住所:静岡県藤枝市藤枝4-3-7
- 過去開催したイベント名:第3回 天下一闘茶会(2015年から毎年開催)
- 参加費:1500円
- URL:https://shizuoka-onpaku.jp/fujieda/toucha
宇治茶道場 匠の館
- 住所:京都府宇治市宇治折居25-2 宇治茶会館
- 過去開催したイベント名:茶香服(利き茶ゲーム)
- 参加費:2000円(5種5煎競技)・1500円(5種3煎競技)
- URL:http://bit.ly/2vt6e12
福寿園 京都本店
- 住所:京都府京都市下京区四条通富小路角
- 過去開催したイベント名:お茶講座 茶歌舞伎体験(要予約)
- 参加費:1,620円
- URL:https://www.fukujuen-kyotohonten.com/kyo-no-chagura/
まとめ
闘茶は、楽しみながらお茶を深く知れる遊びです。
イベントに参加しなくても、複数の種類のお茶を用意すればご家庭で気軽に闘茶を楽しむこともできます。
お家に人を招いた際に闘茶をして遊ぶなんていうのも優雅で良いですね。
皆さんも機会があれば闘茶に挑戦してみてはいかがでしょうか?
当社おすすめのお茶はこちら
宇治茶(玉露)
| 商品名 | 玉露茶 |
| 商品区分 | 食品・飲料 |
| 内容量 | 100g |
| 原材料名 | 緑茶 |
| 原産地 | 京都府宇治市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 高級な京都宇治市の玉露茶です。 老舗のお茶屋がこだわり抜いた玉露茶を是非お試しください(^-^)/ |
巣鴨 参拝茶
| 商品名 | 特選参拝茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 100gまたは200g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本[Made in Japan] 静岡県掛川市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 当店で一番人気の参拝茶の良いところだけを集めたお茶です。 参拝茶では物足りない人にはオススメです(^-^) |
とげぬき地蔵茶
| 商品名 | とげぬき地蔵茶 |
| 商品区分 | 飲料 |
| 内容量 | 【1袋あたりの内容量】 100gまたは200g |
| 原材料名 | 茶葉 |
| 原産地 | 日本[Made in Japan] 静岡県掛川市 |
| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |
| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |
| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |
| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |
| 店長の一言 | 当店限定の巣鴨とげぬき地蔵茶です。 参拝茶と比べて、茎を抜いてあり、渋い味が特徴的です(^-^) |
最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)
- ルイボス茶のカフェイン量は?飲み過ぎるとどうなる?栄養成分についても - 2025年7月5日
- 「書院の茶」と「草庵の茶」の違いは?書院茶室で行われる貴族たちの嗜み - 2025年6月30日
- 赤ちゃん番茶の特徴とは?カフェインやタンニンがほぼ含まれず、すっきり飲みやすい - 2025年6月29日













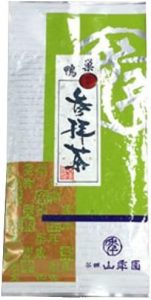
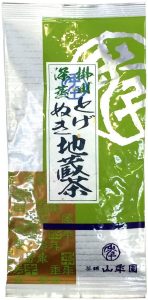


 山年園でお買い物
山年園でお買い物

